トップページ > 2012年
登記完了証とは、オンライン申請、書面申請を問わず、登記手続きが完了したときに法務局(登記官)から申請人に対して交付される登記手続きが完了した旨の書類です。申請人が2人以上いるときは、その1人(登記権利者及び登記義務者の各1人)に通知されます。
通常、登記完了証は、登記識別情報とともに綴られていることが多いですが、従前の登記済権利証の代わりとなる登記識別情報通知とは違い、その後の登記申請に使用することはありませんので、紛失したとしても問題ありません。
関連記事
権利証と登記識別情報通知
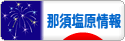
にほんブログ村
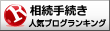
相続手続き ブログランキングへ

Q 相続分の譲渡とは?
A 相続分の譲渡とは、遺産全体(積極財産・消極財産)に対して共同相続人の1人が有する相続人たる地位を譲渡することです。相続分の譲渡がされると、譲渡人が有する一切の権利義務が包括的に譲渡人に移ります。有償・無償を問わず、相続分の一部を譲渡することもできます。
Q 相続分の譲渡の相手は他の共同相続人だけ?
A 相続分の譲渡の相手方は、共同相続人に限られず、共同相続人以外の者にも譲渡することができます。相続人以外の者が相続分の譲渡を受けた場合、譲受人は遺産分割協議に参加することができます。
Q 相続分の譲渡がされた場合、遺産分割協議はどうするば良い?
A 相続分の譲渡をした相続人は、遺産分割協議から抜けることになります。なお、相続分の譲渡は遺産分割協議前に限ってすることができます。

遺言があっても、相続人全員が遺言の内容を知っている場合、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含みます)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることはできるとされています。判例も遺言と異なる内容の遺産分割を認めています。
また、遺言の存在を知らないで遺産分割協議をしてしまった後に、遺言が出てきた場合には、遺産分割協議が錯誤により無効となりますので、再度遺産分割協議をすることになります。
なお、遺言執行者が選任されている場合には注意が必要です。遺言執行者は遺言の内容を実現するために選任されていますので、いくら相続人全員が同意したからといって、遺言執行者に無断で遺言とは異なる内容の相続手続きをすることはできません。遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割もできるとされています。

